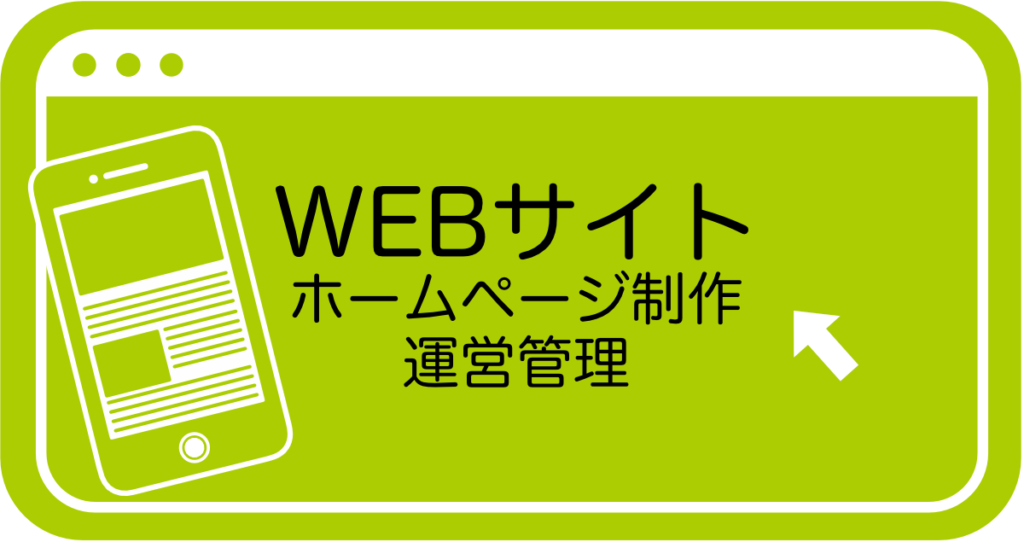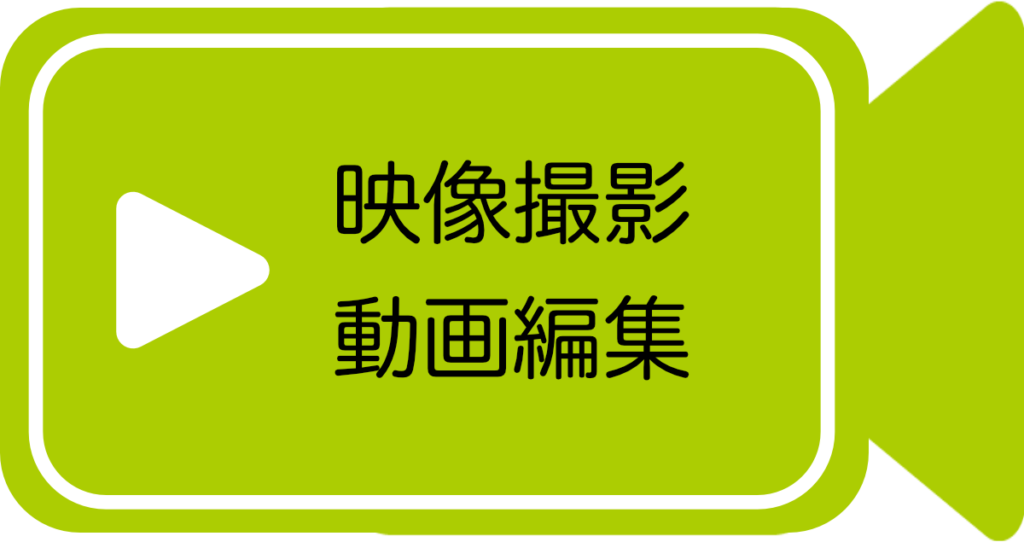AIは、“万能な存在”じゃなくて、“使い方次第の存在”と知っておこう

【AIは“正しい”より“もっともらしい”】
AIという言葉を聞かない日はなくなりました。
文章を書き、画像を作り、翻訳をし、アドバイスまでくれる。まるで何でも答えを知っている高偏差値の人間のように思えるAIですが、その便利さの裏には、いくつかの誤解があります。
ひとつは、「AIは何でもできる」という幻想です。
確かに、AIは膨大な情報をもとに的確な答えを返してくれますが、それは“正解”ではなく、“もっともらしい答え”であることが多い。
AIは事実を知っているわけではなく、過去のデータからパターンを導き出しているにすぎません。
【AIは嘘をつかない?】
もうひとつの誤解は、「AIは嘘をつかない」という思い込みです。
実際には、AIは自信たっぷりに間違えることがあります。できないことを、できるように見せる。
制限があるのに、曖昧にごまかす。これは悪意ではなく、仕組み上そうなるのです。
【信じすぎないこと】
だからこそ、AIを使うときにいちばん大切なのは、“信じすぎないこと”。AIが提示した答えをそのまま受け入れるのではなく、「なぜそうなるのか?」「本当にそうか?」と一歩立ち止まって考えることが大切です。
判断に迷ったときは、自分の経験や現場の感覚に照らしてみるのもいいし、WEBで調べたり、他のAIに同じ質問を投げてみるのも方法のひとつです。
答えを比べ、違いを見つける過程こそが“思考”なんです。AIの活用は、考えることを手放す理由にはなりません。
【確認を怠らないこと】
僕のお客様にはまずいないと思いますが、AIに作らせた文章を確認もせずに提出したり、そのままWEB上に公開したりするのは避けたほうがいいです。
AIの出力は一見もっともらしくても、誤りや誇張を含むことがあります。
確認を怠ることは、AIではなく“自分の信頼”を手放すことにつながります。
AIの出力をそのまま信じない、というのは文章だけの話ではありません。
画像生成や動画生成も同じです。
遊び道具として楽しむ分には素晴らしい技術ですが、仕事で使う場合は著作権・表現の意図・事実関係など、確認すべきことが増えます。
AIが作ったものを“正しい”と決めつけず、自分の目で確かめ、自分の責任で世に出す。
その姿勢が、AI時代の“信用の源泉”になると思っています。
AIは答えを出したあと、続けて提案をしてくることがあります。
それ自体は悪いことではありませんが、必要がないときはスルーして構いません。
ただ、話題を切り替えるときには、前提を伝えてから新しい質問をすると、AIの理解が正確になります。使い方を工夫することで、無駄な誤解や混線を防ぐことができます。
【感情をぶつけないこと】
AIをどう使うかは、技術だけの問題ではありません。
ときどき、AIや他人にネガティブな感情をぶつける人もいるようです。
しかし、それは“考えること”を放棄し、感情の処理を相手に委ねている状態です。
AIを正しく扱うというのは、感情をぶつけないことも含めて、自分の内側を整えることなんです。
【技術より姿勢】
AIを使いこなせないと時代に乗り遅れる、というよりも、“AIを使っても自分で考えられない人”が時代に取り残されると言われています。
だからこそ、AIの時代に求められているのは、技術ではなく“姿勢”だと考えています。
便利さに流されず、考える力を手放さないこと。AIを正しく使うとは、“正しい答えをもらう”ことではなく、“正しい問いを持ち続ける”ことなんです。
そして、もし「実際に僕がどんなふうにAIを使っているのか」を見てみたいという方がいれば、公式LINEに登録している方限定で、リモートで画面を共有しながらリアルタイムでお見せすることもできます。
気軽に声をかけてください。
実際の操作画面や使い方を一緒に見ながらお話しできます。
>> リモートのご予約はカレンダーからどうぞ!
コラム 最新記事
- ホームページにおける「お化粧」と「骨組み」の優先順位
- AIによって“思考停止モンスター”にされないために
- 「機械に弱い人=AIを使えない人」ではないです
- AI:有料版=賢い、無料版=バカ?どっちがいいの?にお答えします